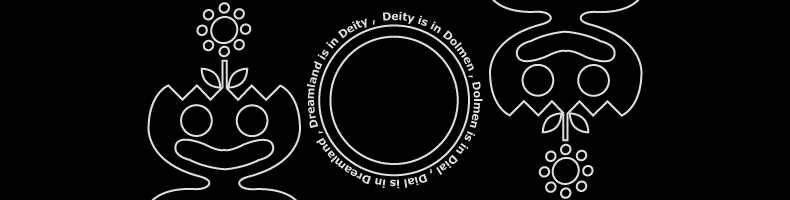「携帯がまた変なの。なんかこわいよ……」
この前の彼女から、また電話がかかってきた。
前回は契約を終えた携帯が毎朝7時に鳴るので怖いと言ってきたが、今回はいったいどんな騒ぎだろうか。
「変なのは新しい携帯? それとも古い携帯?」
「古い方なんだけど。あ、ケーキ食べちゃって」
私は遠慮なくフォークを手にして、イチゴのショートケーキを口にしながら答えた。
「ああ、あのピンクの、この前騒いでたアレか。またアラームがおかしくなったとか?」
「アラームは鳴るんだけど……おかしいの」
「なにが?」
「あの時笑われてから、結局目覚まし代わりにあの携帯を使ってたの。毎朝7時に必ず鳴るから便利かな、って思って」
「良かったね」
「でもね、ある日鳴らなくなったの。充電は出来てたんだけど、なぜかアラームが鳴らなくなって。だから捨てちゃったの」
私が黙っていると、彼女は続けた。
「でもね……ちゃんとアラームは鳴ったの」
「捨てたはずなのに?」
「そう……捨てたはずなのに、気が付いたら部屋の中にあのピンクの携帯が置いてあって、朝7時にアラームが鳴るの……」
「気のせいじゃ?」
「私もそう思ったんだけど、気のせいじゃないの。何度捨てても、戻ってくるの。ビニールにくるんだりしても、元通り戻ってきてアラームが鳴るの」
「電池を取れば鳴らなくなるんじゃ?」
「私もそう思って、裏蓋を開けて充電池を取って、携帯と充電池を別に捨てたんだけど、充電池がセットされた状態で戻ってきちゃうの。そしてアラームが鳴るの……毎朝」
「それは……怖いね」
「あまりにも怖いから、知り合いの警察の人に見せてみたんだけど、指紋も何も出ないの。不自然なくらいキレイに拭き取ってあって、誰の仕業か分からないの」
「そうなんだ」
私がケーキを食べ終えたので、彼女が皿やフォークをしまい始めた。
「でもね、手がかりがあったの」
私が黙っていると、彼女は続けた。
「携帯の表面には指紋がなかったんだけど、裏蓋には指紋が残ってたの」
そう言われた瞬間、私は自分がさっきまで使っていたフォークを見た。
すでに彼女はハンカチでフォークをくるむようにし、余分な指紋が付かないようにしていた。
嗚呼。
「できれば、このまま騒ぎ立てたくないから……できれば、自分から言って欲しくて、それで終わりにしたいから……だから……」
彼女は悲しそうな瞳で私を見ている。
私は彼女から視線をそらし、自分の手元を見た。
そこには彼女とお揃いの、いや、お揃いだった、携帯がある。
「どうしてこんなことしたの、千尋ちゃん……?」
あの時二人で一緒に選んだ、ピンクの携帯。
なのにどうして捨てようとするの?
私は怖い。
こんなことも分かってくれない、彼女の鈍感さが。
気がつくと、いつのまにか無意識に手が伸びていた。
彼女の目の前にある、まだ使われていないフォークへと。