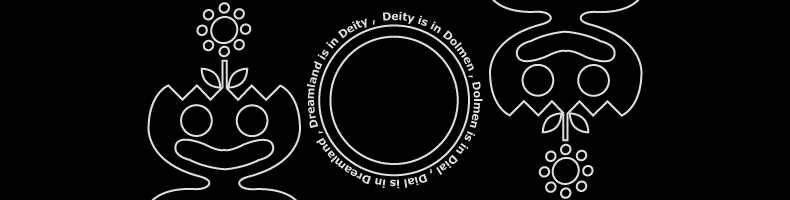彼女と出会ったのは、とあるネット上のサークルがきっかけだった。
浮世離れしていて丁寧な言葉使いをしていたが、実際に会うまでは女性だと思ってなかったので普通に驚いた。
まぁ、そういう女性的な話題が出る場でなかったので、分からなくても無理はなかったのかもしれないが。
実際に話してみると、ネット上の文章が作り物ではなく、彼女自身のそのままの言葉が文字として紡がれているのだと分かった。
ネットそのままの非現実的な雰囲気が気になって、どういう生活をしているのかと聞いてみると、両親の遺産で一生遊んで暮らせるので気ままに生きていると教えてくれた。
お金だけあっても、満たされないですよ。
金持ちならではの傲慢なセリフに聞こえそうだが、その言葉の響きには切実なものが感じられたし、表情は全く笑っていなかった。
私もその意見には賛成だ。本当に欲しいものはなかなか手に入らない。だから私たちはこのサークルに入って、自分の歪んだ渇きを少しでも潤せないかとネット上で愚痴る。そうする他に術が無いから。
やっぱり、若いうちがいいですよ。
願いごとの話をすると、決まって彼女はこう言ったものだ。
年老いてから自殺するなんて、もってのほか。首吊りが好みなんだけど、安らかに横になっているのも捨てがたい。どちらかを選びたいんだけど、未だに決めきれない。
そんなとりとめのない話をしていたが、しばらく彼女と連絡が取れなくなった。
遂に彼女はどちらかの手段を選んだのだろうかと思い始めた頃、メールが届いた。そこにはとある山奥の住所が記載されていて、最後にはこう書かれていた。
願い事がかなうと思いますよ。
意味は分からなかったが、言いようの無い期待に突き動かされ、私は平日にもかかわらず即座にその場所へ出かけた。
タクシーを乗り継いで、その館の目の前に着くと、建物の中からモーターのような音が聞こえてきた。
大きな扉は鍵もかかっておらず、私はなんなく中に入り、音がする地下室へと降りていった。
丸い部屋の中央で、黒いビニールにくるまれた物体が回っていた。
黒くなければ、それは巨大なボーリングのピンのように見えなくもなかった。首のような部分にはロープが巻きつけられていて、凄い勢いで回転しているせいで、遠心力により向きが水平に保たれている。
黒いビニールで中が見れないが、私は確信していた。
あれは、首吊りをしながら、水平に横たわる彼女だ。
なるほど、彼女の願いは同時にかなった事になる。
その事実に安堵した瞬間、気づいてしまった。私の願いはかなっていない。
彼女と明確な約束をしたわけでもない。だが、二人で願いをかなえたい、そう思う気持ちは以心伝心だったのではないか、と夢見ていたのに。あれは私の勘違いだったのだろうか。
私の願い。
言葉を選ばなければ、私はマゾだ。それも重症の。
たまに行き過ぎたプレイのせいで、病院にいった時は「大丈夫、医者には守秘義務があるから」と言われるくらいの。
そんな私なりに色々な「遊び」を試してきたが、結局はこのようなシンプルな願いに行き着いてしまった。
女性に蹴られて死にたい。
それを一度でも意識してしまうと、その妄想の虜になってしまい、逃れることは出来そうに無かった。
彼女の足は細く、力も無さそうだった。
念のためにと聞いてみたが、スポーツなどの経験もないので、彼女によって私の望みが適うことは難しいだろうと思い知らされただけだった。
あなたの願いをかなえるために体を鍛えるのも面白いかもしれないけれど。
そう彼女は言っていたが、あの笑顔からすると完全に冗談だったのだろう。今思えば、彼女の笑顔を見たのはあれが最初で最後だ。
記憶の中の彼女の笑顔を思い出しつつ、現在目の前で回転し続ける「彼女」を見ていた。
記憶と視界が重なると、まるであの黒い袋の中で、彼女が笑顔になっているのではなかろうか、と思ってしまう。
しかし凄い勢いだ。まるで巨大な扇風機のようで、指を突っ込めばただじゃ済みそうに無い。
そう思った瞬間、私はやっと彼女の心遣いに気づいた。
今まで私は彼女にプレイを要求したことはないばかりか、手を握ったことすらなかった。
そんな私が、はじめて彼女に触れる日がやってきたのだ。
私は彼女に向かい、足を踏み出した。
そこに鏡は無かったが、確信している。私は今までの人生の中で、もっとも歓喜に満ちた表情をしていたいに違いない。
回転する彼女の足に頭を突き出しながら、私は確信していた。
私たちの三つ目の願いは、もうすぐ、叶う。