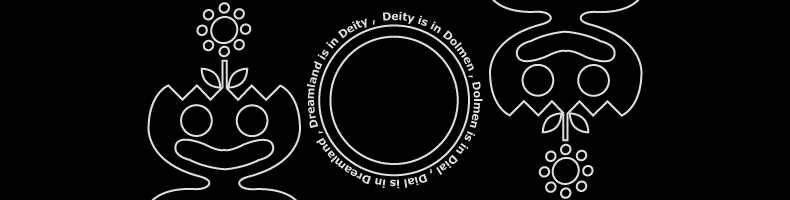夏が始まった。
いつになったらこの暑さは終わるんだろうか。
蒸し暑く寝付けない夜が続いていたが、最近は寝付けないほうがいいようにさえ思えてきた。
なんだろう、あの嫌な夢は。しかも毎日のように。
私は井戸の底に居る。生き埋めにされているのか、首から下が全く動かせず、顔はずっと上を向いたまま、下を見ることも出来ない。
こうして見上げていると、はるか上に小さな白い丸、おそらくは井戸の入り口と思われるものが見える。あまりに距離がありすぎるのか、そこに空があるのかも分からないし、そもそもこの井戸と思われるものが屋外にあるのかすら分からない。
すると、人影らしきものが見えた。影になっていて、距離もあるため、その表情は全く分からない。しばらくこちらを見下ろしていると、片手を持ち上げて、手のひらを開いた。
落ちてくる。
何かが落ちてくる。
何が落ちてくるのだろうか。
いつもそこで目が覚める。
かなり気味が悪いのだが、いつしか眠ってしまうとこの夢を見てしまう。そしていつも何かが落ちてくるところで目が覚める。この夏はこの繰り返しだった。
そうして今夜も同じ夢を見てしまっている。
あまりに何度も見てきたせいか、最近は不気味さも消えうせてきて、ああまたか、と達観した思いで落ちてくる何かを見ていた。どうせまた、ここで目が覚める。
なぜ気づかなかったんだろう。
毎日同じ夢を見ているとばかり思っていたが、毎日少しずつ様子が変わってきている。
最初は黒い点のように思えていた何かは、今日は黒豆くらいの大きさくらいだ。
そうか、夢を見るたびに、少しずつあれは私に近づいてきている。
いったい何が落ちてきているのか。そして私の上に落ちてきてしまうとどうなってしまうのか。
たかが夢、されど夢。
見たいような、見たくないような。
確かめたいような、確かめない方がいいような。
そんな相反する思いのまま、結局は睡魔に勝てずにまどろむ私の目前に、”あれ”は迫りつつあった。
そして夏が終わろうとしているある夜、黒い点はピンポン玉くらいになり、その輪郭くらいははっきり分かるようになってきた。
見ないほうがいいかもしれないとは思ったが、夢だからなのか目を閉じることも目を逸らすことも出来ない。
それに見たいという気持ちが無いと言えば嘘になる。
私は目を凝らしてそれが何なのか確かめてみた。
最初はピンポン玉かと思った。だがその白い玉の中央には黒い丸があった。そうだ、これは眼球だ。
まさか。
夢の中で生き埋めになってるはずの腕はすんなりと動き、私は自分の瞼に手を当てていた。
そしてその瞼の不自然な空洞に気づいてしまった瞬間、私は二度と夢を見ることは無くなった。そして光を見ることも。
夏が終わらない。
いつになったらこの暑さは終わるんだろうか。