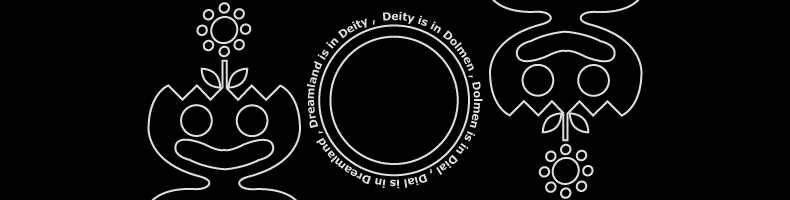朝、出社前の忙しい時間。玄関を出ようとしたところで、妻に、なにかがとびかかってるのが見えた。
「なにかがとびかかっているよ」
そう声をかけるぐらいしか余裕がなく、彼女がなにかがいないかと気をめぐらす様子を尻目に、急いで玄関を開け駅へと走った。
やっとのことで電車に乗り込み、息が落ち着いた頃、メールが届いた。
「無事に実家に着きました。こっちはもう暑いよ」
妻からのメールだった。
そうだった。妻は昨夜から夜行列車で実家に帰っていたのだった。
だから今朝、自宅に妻がいるはずは、ない。
あれは夢だったのだろうか。
いや、今さっきの出来事じゃないか。
まさか、妻に何かがあって、虫の知らせか何かが。
満員電車と困惑とで落ち着かないので、せめて外でも見ようと目の前の窓を眺めようとしたが、あいにくの空模様で辺りは暗く、窓は鏡のように社内の様子を映し出していただけだった。鏡と化した窓の向こう、見覚えのあるものが写っていた。
私の、顔。
その瞬間、記憶と今の視界が重なった。
さっきも同じ顔を、見た。
そうだ、私が今朝見かけたのは、姿見の向こうの、私自身だ。
その顔を見て、ふと手元の携帯をあらためて見た。
派手なピンクの可愛らしい携帯。
そうだ、これは、妻の携帯だ。
再び窓の向こうを、私の顔を、見る。
そうだ、私は、妻だ。
実家に帰っているのは、私の旦那の方だ。
何もかもが分からなくなった私の目の前、窓の向こうに、なにかが見えた。
“私”にとびかかってくる、なにかが。